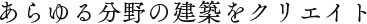現在の集成材の原理である寄木造り・合成柱の技法
世界最大の木造建築物と言えば、東大寺大仏殿でしょう。
その大仏殿と大仏様はこれまでに2度の大きな戦に巻き込まれて焼け落ちています。
758年、聖武天皇が創建⇒1181年の戦火⇒1190年、重源が再建⇒1567年戦火⇒127年間、大仏様は資金不足などで木造銅板張りの仮の頭を乗せた状態で雨ざらしだったそうです。
現在の大仏殿は江戸時代、1709年になりやっと3代目が14年の年月をかけ、公慶によって再々建されたものです。
300年以上前に東大寺の大仏殿の柱が寄木造りで巧み造られているのをご存じですか。あの高さ48メートルの柱を造るのに、集成材の技法が使われています。昔のように長大材を集めることが、困難であったため、柱は長さを4箇所継ぎ(柱1本に12本の捌木を交互に繋ぐ)、直径も台形の捌木を寄せ集めて太くするという方法(合成柱)で造られました。造られました。現在の集成材の技術が300年以上も前に取り入れられていました。


この合成柱は、12角形の真柱の周囲に樽のクレ材(側板)のように捌木という材を寄せ合わせ、ニカワ(膠:古来の接着剤)を入れて、鉄の胴輪で締め付け、犬釘を打ち込むことで大径材を造り上げました。犬釘とは、新橋で汽車が走った時代から線路を固定するために、枕木に打ち込んだ犬の頭のような釘のことで、現在でも見られます。文献によると、総柱60本を造る為には、捌木3200本を使っていると言われています。


▲12角形の真柱の周囲に捌木材を寄せ合わせニカワで固め、鉄の胴輪で締め付け、犬釘を打ち込む
重源や公慶などの先人達が培った合成柱などの匠の技が小径材から大径材を造り出し、大型木造建築物に必要な大径材の不足を補っていたのです。しかし、300年以上前から「現在の集成材の原理とも言える寄木造りの技法」が寺院建築や東大寺南大門の金剛力士像などの仏像に使われていたことから、技術の誕生と発展は、時代背景と密接な関係にあることを改めて実感しました。